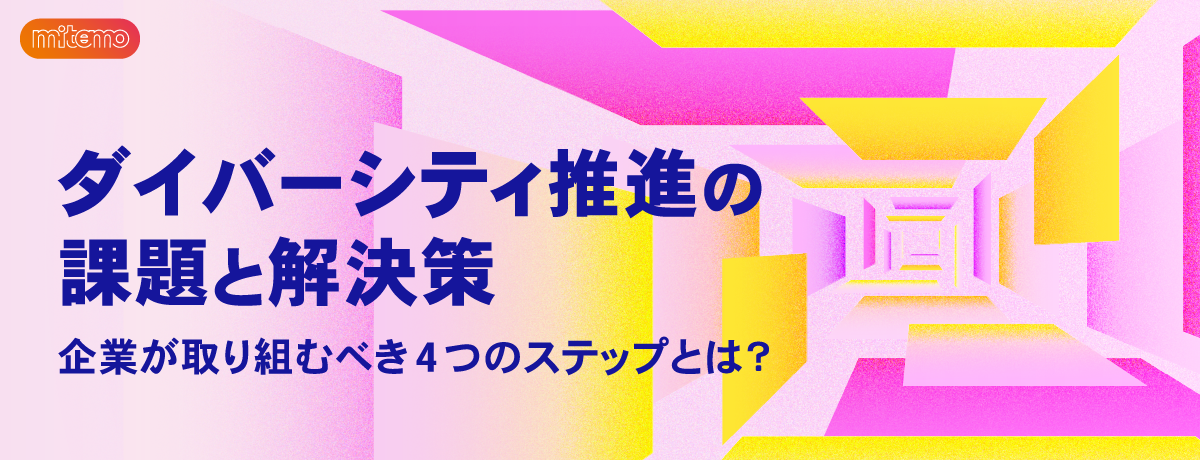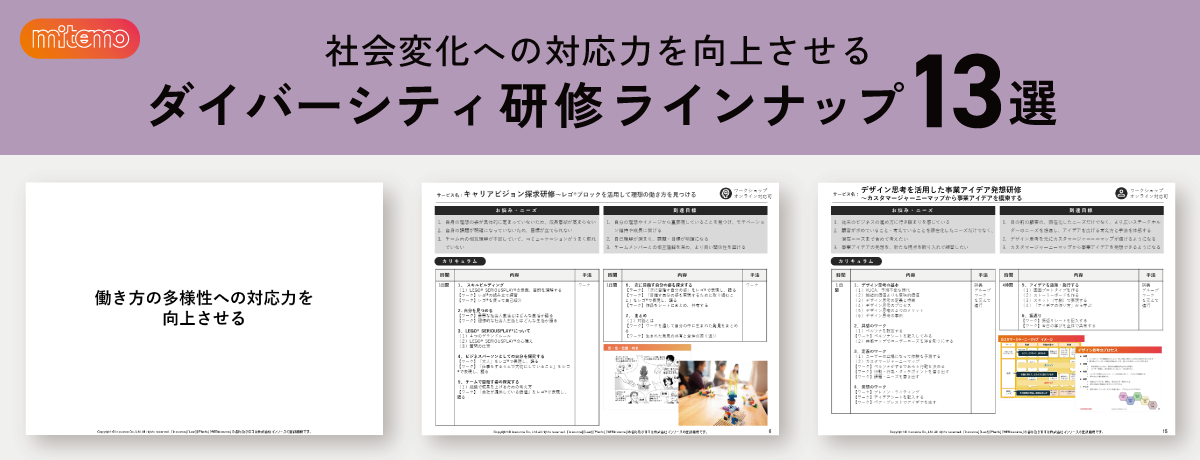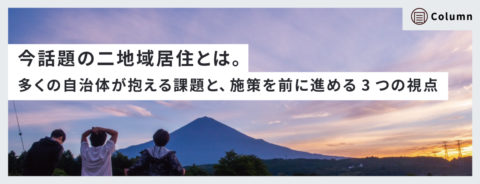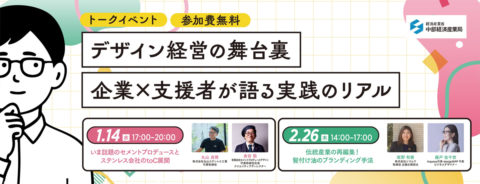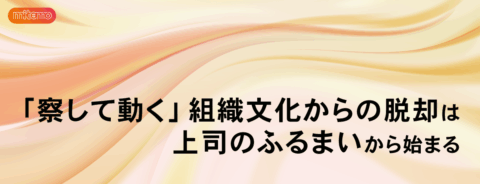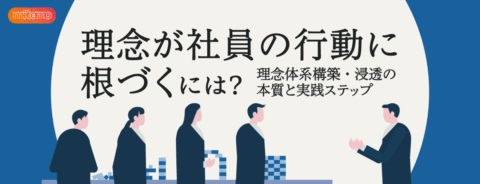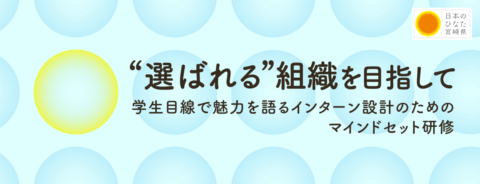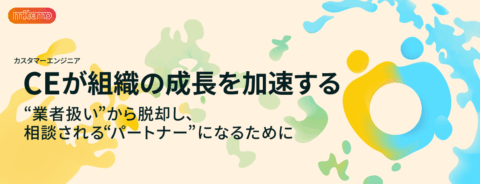近年、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)は、企業が競争力を維持・強化するうえで、今や欠かせない視点となっています。多様な人材を受け入れ、その能力を最大限に活かすことで、新たな価値創出や生産性向上が期待できます。しかし、多様性を活かすためには、単に制度を整えるだけでなく、組織全体の意識改革が必要です。
一方で、ダイバーシティを推進しようとする企業の多くが、具体的にどのような施策を講じるべきか悩んでいます。単に多様な人材を採用するだけでは、組織の成長にはつながりません。むしろ、職場の価値観や文化の違いが摩擦を生み、生産性を低下させるケースもあります。では、ダイバーシティを実現し、組織の成長へとつなげるには、どのような課題に取り組み、どのようなステップを踏むべきなのでしょうか。
ダイバーシティ推進における主な課題
ダイバーシティを推進する過程では、多くの企業がさまざまな壁に直面します。その中でも特に影響が大きいのが、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)、異文化理解の不足、そしてジェンダーギャップです。
無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)
私たちは日常的に、性別、年齢、国籍などに基づく固定観念を持ち、それが意思決定や評価に影響を与えています。例えば、「リーダーは男性の方が適している」「外国籍の社員は日本の商習慣を理解しにくい」といったバイアスが、昇進や人材配置の機会を制限し、組織の多様性を阻害することがあります。
異文化理解と多文化共生
近年、外国籍社員の採用が増加し、グローバル市場でのビジネスが活発化する中で、異文化理解の重要性が高まっています。文化的背景の違いによる価値観のズレが、職場における誤解や対立を生むこともあります。そのため、異文化コミュニケーションのスキルを養うことが求められます。
ジェンダーギャップと女性活躍推進
女性管理職比率を向上させる取り組みが進められていますが、依然として無意識のバイアスや育成機会の不足が課題となっています。「女性は家庭を優先したいのではないか」といった固定観念が、女性自身のキャリア選択に影響を与えるケースもあり、それが結果的に管理職登用の機会を狭める要因となっています。
課題を解決するためのステップ
1. 現状の可視化と具体的な課題の洗い出し
まず、組織の現状を正しく把握することが重要です。従業員意識調査を実施し、職場環境や働き方に関するデータを収集することで、問題点を明確にできます。調査の際には、「上司・同僚の発言で心理的安全性を脅かされたことがあるか」「キャリア形成において性別や国籍の影響を感じたことがあるか」など、具体的な質問を設定することで、従業員の抱える課題をより明確に把握できます。
また、アンケートだけでなく、異なる属性の従業員同士が自由に意見を交換できる場を設けることも有効です。特に、外部のファシリテーターが入ることで、より率直な意見が引き出されやすくなり、社内では気づきにくい課題が見えてきます。
2. 意識改革を促すための働きかけと研修の導入
課題を明確にした後は、意識改革を進めるステップへ移行します。無意識のバイアスに気づき、行動を変えるには、実践的な学びの場が欠かせません。
例えば、評価におけるバイアスを低減するため、評価対象者の名前や性別を伏せた状態で選考を行う手法を導入することで、公平性が向上します。また、会議で特定の層の発言機会が少ない場合には、心理的安全性を高めるためのファシリテーションスキルを活用し、発言しやすい環境を整えることが有効です。
さらに、研修の実施も意識改革に大きく寄与します。例えば、ロールプレイ形式でアンコンシャスバイアスの影響を体感できるワークショップや、多文化共生を促進する異文化理解研修を導入することで、参加者の認識を深めることができます。特に、日常業務を想定したケーススタディによって、受講者は具体的な行動イメージを持つことができ、実際の行動変容につながります。
3. 仕組みや制度の見直しと実行可能なアクションプランの策定
意識改革だけではなく、それを支える制度や仕組みの整備も必要です。例えば、男性育休の取得率向上を目指す場合、単に取得を推奨するだけではなく、上司や同僚の理解を深め、取得を前提とした業務設計を行うことが重要です。管理職が一定期間業務を離れても組織が円滑に回る仕組みを整えることで、育休取得のハードルを下げることができます。
また、ダイバーシティ推進に向けた施策として、従業員のキャリア支援制度を見直すことも有効です。育児や介護との両立を支援するため、フレックスタイム制や在宅勤務制度の柔軟性を高めることで、多様な人材のキャリア継続をサポートできます。
4. モニタリングと改善のサイクルを継続的に回す
施策を導入した後も、定期的なモニタリングを行い、状況に応じて柔軟に改善していくことが重要です。企業ごとに課題は異なるため、一度決めた施策が最適とは限りません。従業員の声を定期的に収集し、施策の効果を検証することで、より実効性のある改善が可能になります。
例えば、女性の管理職登用を推進する施策を導入した場合、単に数値目標を掲げるだけでなく、管理職候補となる女性社員へのサポート体制を強化することが求められます。メンター制度やスキルアップ研修を組み合わせることで、実際に活躍できる環境を整えることができます。
また、ダイバーシティ推進の取り組みが一部の層に偏らないよう、男性社員への意識改革も並行して進めることが重要です。例えば、「女性活躍推進=女性だけの問題」と捉えられると、組織全体の協力が得られにくくなります。男性社員も巻き込んだワークショップや、家事・育児を担う男性社員のロールモデルを紹介する機会を増やすことで、組織全体の意識を変えていくことができます。
実際にミテモがご提供した事例についてはこちらからご覧いただけます。
まとめ
DE&Iの推進は、一度の取り組みで完了するものではなく、継続的な改善が求められます。組織の現状を正しく把握したうえで、意識と制度の両面から改革を進め、すべての人が公平に活躍できる環境を整えることが重要です。
それぞれの企業が抱える課題は異なりますが、障壁を乗り越えながら具体的なステップを積み重ねていくことで、持続可能なダイバーシティ経営が実現します。
社会変化の対応力を向上させるダイバーシティ研修について、まとめた資料を以下のバナーからダウンロードできます。
またダイバーシティ推進に関するサービスの詳細について伺いたい場合は、些細なことでも結構ですので、以下の問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。ぜひ、この機会にダイバーシティ推進施策を見直してみませんか?